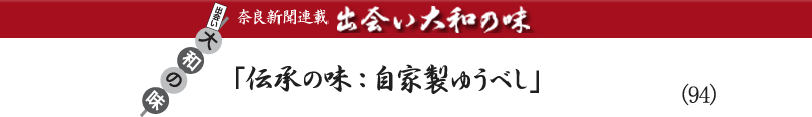|
①柚の収穫:2~3回霜したら柚を収穫する。11月末頃になる。イエの裏山には3本の柚の木があり、毎年100個の柚を収穫しても余る程だが、今年(H、18)は異常気象によって半分の柚が腐り、収穫は50個だった。
②ゆべしの具:餅米を一度洗って陰干ししたもの5合、乾燥椎茸3合ほど、落花生3合、花鰹3合ほど、ゴマ1合、ダシの素1合、七味唐辛子1合、味の素5勺、砂糖600g、以上の全てをミキサーで粉化したものと、地味噌(自家醸造味噌のことを十津川村では地味噌といい、その大半が麦味噌。中前さんの地味噌は4斗桶に3合塩で仕込み1年以上寝かせたもの)3kgを混ぜ合わせ、具とする。材料のほとんどが自家製のもので、その時ある物次第で具を作る。地味噌でないと家風のゆべしの味にはならない。
③ゆべし製造・蒸す:以上の具をもって、柚の収穫から一週間後にゆべしの仕込みをする。収穫した柚は一週間おかねば皮が破け易い。まず、柚を釜と蓋に切り分けるが、端を少し残して完全には切り離さない。次に柚の果肉をスプーンでくり抜く。先に作った具を6分目まで柚釜に詰め、それを庭先にある竈でとろ火で3時間蒸す。この火加減に熟練を要す。
④ゆべし製造・干す:蒸しあがれば笊にあげ、触れて手につかなくなるまで干す。20日間以上干すことになる。きちんと蒸してしっかり干せば、室温で一年保存しても柔らかみの残るゆべしが出来上がる。
⑤食べ方:薄くスライスし、酒肴、弁当のおかずとして食す。丸のままかじる人もいる。
⑥果肉の利用:果肉は笊にあけ、汁を取り、その汁に塩一つまみを入れて冷蔵庫で保存する。握り込み(江戸前)の秋刀魚寿司の調味料とする。
|