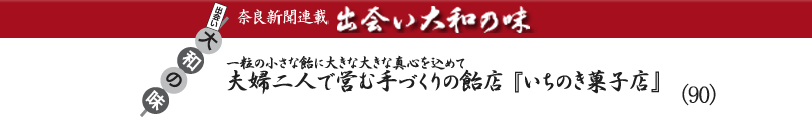|
「けんかをすると飴に角(つの)がでるので、けんかはしませんよ。」そう言って笑うのは
櫟木春美さん(54歳)だ。春美さんは元小学校の先生。先代の娘さんだ。
子供の頃から先代の飴づくりを見て育ち、仕事の傍らお店の手伝いをしていた。
その先代が亡くなり、3年ほど閉めていたお店を再開させる決意をさせたのは、ご近所の人や常連の方々の「早くお店を開けて欲しい。」との声だった。
2年前までサラリーマンをしていた夫の良夫さん(57歳)と共に飴づくりの練習に励んだ。
「おじいちゃんの味はもう少し濃かったよ。」いつも飴を食べてくれていた常連さんたちがこうアドバイスをしてくれた。お客様が先生。
飴は毎日必要な量だけ作られる。作り方も、作るための道具も昔ながらのものだ。
まず、水、砂糖、水あめを鍋にかけ、焦がさぬようかき混ぜながら煮る。180℃もの熱をもった飴を鍋から盥(たらい)に移し、冷たい水がたっぷりと入った水槽にその盥ごと浮かべて一気に冷やす。飴がある程度固まったら、作業台にのせ、手で棒状にのばしていく。それを球断器にかけると、一口サイズに丸まった飴がゴロゴロと現れる。その一粒一粒を手際よくセロファン紙に包んでいく。
たった今出来上がった飴を一ついただいてみた。
まだほんのりと温かい飴は、甘すぎず、少し緊張していた気持ちをほっと和ませる。
ふとこんな光景が脳裏に浮かんできた。仕事の合間や勉強に疲れたとき、誰かがこの飴を一粒ほおばる姿。どこかへ旅行に行く列車の中、仲間と会話をしながら、思わずこの飴を口に入れる誰かの姿。
この飴はいつも誰かのポケットに備えられている。昔からずっと。
櫟木さん夫婦は一年の内、7月から9月半ばまで夏休みをとっている。
「夏の暑さや湿気が飴に良くないから。」と。
二人はその期間を新しい飴の開発や先代の味に少しでも近づくための練習に費やしている。
櫟木さん夫婦の一粒の小さな飴に込めた大きな大きな真心と夢。
「どこにも売っていない飴を作りたいんです。」という二人は今日も夫婦仲良く飴づくりに励んでいる。
|