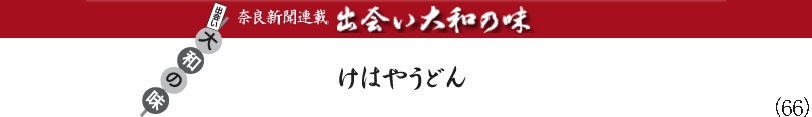|
長い夏であったが、秋をを越え急に冬がやってきた。そろそろ温かいものが恋しい季節。アツアツのうどんをズルズルっと音を立てながらいただくのもおつなものである。関西文化の「こなもん」の中でもうどんはほど広く親しまれているものはない。
顎(あご)の力をあまり使わなくてすむ、やわらかい絶妙の食感のうどんは、現代人にぴったりの食べものである。

|
大きく分けてうどんは、麺(めん)コシの強い讃岐うどん系。麺がもちもちした軟らかい関西うどん系に分けることができる。腰の強い讃岐うどんは、煮込んで味をたっぷり含ませたる、堅めでよく噛(か)んでいただくところから、麺本来の旨(うま)みを引き出す食べ方が適している。
関西のうどんはやわらかく、のど越しを優先しているために麺そのものよりも出汁(だし)とのバランスで口内調味での食べ方に適している。お出汁でいただく上方ならではの食文化である。
食べ方により最も適した、それぞれのうどんの名称があってもよいのであるが、いまはこれらすべてを「うどん」で括(くく)られている。これほど親しまれて食べられている、うどん原料の小麦は、ほとんどが輸入にたよっている。
長い間の米作保護農業はその半面、その他の優れた食材の生産を犠牲にしてきた。うどん原料の小麦も例外ではない。現代の多様化した食文化を満たすには、多様化に対応する農業パラダイムシフトの転換が求められる。
葛城市(旧当麻町)大畑の小麦生産農家の増田晃さんは五年前、麦作組合を設立し、国の転作政策で米作りを50%にして小麦の作付けを始めた。
助成金を活用して試行錯誤でなんとか続けてきたが、まだまだ利益が出るには難しいという。
「このへんの土地は二上山麓(ろく)の砂地やから、朝、水をいれても夕方にはあらしません」「手間がかかりますけど、小まめに水を入れ替え、面倒をみてやる分、おいしい麦ができるんと違いまっけ」と生産者の心意気が伝わってくる。
昔から米は西山といわれ、金剛、葛城、二上山麓の砂地の米がうまいとされてきた。
西山は紫外線のすくない朝日をたっぷり受け手育つから、小麦にとっても良いのではないかと思われる。
増田さんら麦作組合の小麦は六月の収穫期には畑のまま地元JAへ引き渡し、収穫から製粉、販売までJAに委託している。
こうして、米からの転作で出来上がった小麦を製粉、手打ちうどんにして販売しているのは道の駅にある「農業法人当麻の家」である。この地粉を使ってのうどん作りをはじめた。うどんの名称は「けはやうどん」。当麻の家で自家生産されたうどんと餅(もち)が入ったきつねうどんである。一杯五百円と観光客のお昼にリーズナブルな価格設定である。うどんは腰がありおいしい。
出汁の味もかつお出汁でしっかりしている。名前から想像するといかめしいがシンプルなうどんである。
けはやうどんの名称は、相撲発祥の当麻のけはやからの由来であるという。
このように日本農業は作物を作るだけの時代ではなくなった。商品づくり、ブランドづくり、販売開発と一貫したマーケティング活動こそに活路がある。増田さんは言う、わしは好きやから農業やってるけど、しっかり儲(もう)かる農業でないと誰も後継者は育たない。しっかり儲かる農業はは、作るだけでなく消費者の口に入るところまで考えんとあかん。
「当麻の家」の地粉を使ったうどんづくりが、新たな観光資源となり得るか期待するところである。
毎年、奈良に三千五百万人の観光客が訪れる。東京ディズニーランド(二千五百万人)と比較しても格段の差である。ただせっかく、来ていただいても特色ある料理や夜の観光施設や宿泊施設が少ない、だから経済効果が少ないという意見もある。
しかし奈良に来ていただく大きな動機の一つは、文化財や自然や風情が残っているからこそである。
そのような観光資源と調和した食文化や観光資源の創出が奈良を元気にするひとつである。
「当麻の家」の地粉でつくるうどんづくりは、食の創造として、今はまだ小さいけれども、新しい観光資源の開発、コミュニティー経済の活性化など新たな活路としての評価に値する。
今後はこの「けはやうどん」を当麻の独自性やインパクトにさらに磨きをかけ、相撲発祥の地ならではの名物化と市場シェア拡大で地域の産業として大きく育つことを期待する。今、まさに農業マーケティングの時代である。

|

|
|