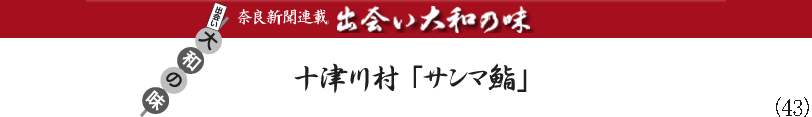|
十津川村では、ずいぶん昔から海の魚となじみが深かったようである。
かつては「遠津川」と呼ばれていたそうだが、その起源には二説あって、一説には、水流長く水上が遠いからだといい、他の一説は山深くして津(みなと)に遠いからだともいう。
その説の起こりはどちらにしても、数十年前までは陸の孤島と呼ばれ、交通の不便な昔から、村の生活に海産物がとり入れられていたことは、村の文化にかかわる歴史的背景にも興味がもたれる。
古くは南北朝時代、村の北部を吉野国、南の方を熊野国に分属されていたというから、村の文化が熊野地方と多くの共通点をもっているのも不思議ではない。

|
村では、山の神を祀(まつ)っている家が多い。なかには二、三軒共同の山の神もある。
ご神体は主に大木だが、岩石などもあって、新しく山の仕事を始めるときなどに祭りをする。
山の神を祭るときは、サンマやサバの姿鮨(ずし)と七個のぼた餅(もち)を供えるところもある。
山の神は女性で、七人の家族があり、海の魚が好きだからだそうだ。
村人が猟に出かけるとき、オコゼの干物を持って山の神に参る習慣がある。オコゼの尻尾(しっぽ)の方をかくして頭だけを見せて、獲物があったら全部見せると約束をしてお願いをする。
次に猟に出るときは頭をかくして尻尾だけを見せて同じことを頼む。これを繰り返すが、猟師は獲物があっても何もしない。全部見せると山の神が笑うからいかんという。
恒例の山の神祭りは地域によっても違うが、おおかたのところ旧暦の十一月七日であり、鮨に適した旬のサンマが熊野灘に回遊してくる季節でもある。
最近ではウルメイワシやサバの姿鮨を作る人も少ないが、サンマの姿鮨は、正月や祝い事のごちそうの一品として欠かせない存在となっている。
十津川村のサンマ鮨には二種類あって、おおまかな地域分けをすれば、村の南北で作り方がまったく違っている。北部の作り方は、塩サンマの塩抜きをした薄塩のサンマを、独特の炊き方をした鮨飯の上にのせ、箱に並べて重石をし、一カ月発酵させた「なれ鮨」なのに対して、南部では、適量の塩をしたサンマを合わせ酢に漬けて鮨にする。
どちらの鮨も、晩秋から初春にかけて回遊してくる脂の落ちたサンマを使う。
村の道の駅では毎週日曜日、農家の女性たちが中心になって「ふれあい朝市」が開かれていて、そこではサンマの旬になると、おふくろの味豊かなサンマ鮨も販売されている。
|