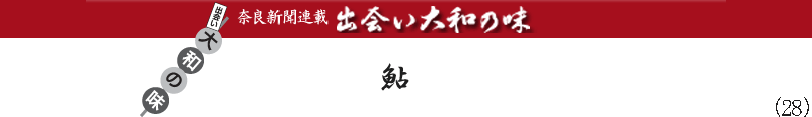|
しばらく、まとまった雨が降らず、ダムの水も少ないというニュースを気にしながら、吉野を訪ねたが、かわらでは家族連れが遊び、腰の辺りまで水につかって釣り人が釣り糸をたれていた。
鮎は川石などについた水ゴケ類を常食とするため、スイカのような独特の香りがするところから香魚ともいい、平安時代の「和名抄」にも「春に生じて夏に長じ、秋に衰えて冬に死す、故に年魚という」
とあるように、年魚ともいわれる。
秋も深まるころ、河口でふ化し、翌年の春、川を上り、9月に入ると卵を抱いて再び川を下る。
この鮎を落ち鮎といい、「さや」という仕掛けなどでとる。
ふだん、目にすることの少ない天然鮎はスマートだ。色も濃い。
吉野川の鮎は、桜鮎といわれるそうだが、何と美しい名なのだろう。吉野漁業協同組合事業部の藤田博さんにそのいわれをお聞きした。
「親の代からの言い伝えですが、吉野川を上ってきた鮎が、川面に散った桜の花びらをコケといっしょに食べるので、この名がついています」
また、鮎は魚ヘンに占うと書くが、鮎のとれ方で、その年の稲の出来具合いを占うという言い伝えが、川上神社に残っているともうかがった。
以前、吉野川の鮎は紀ノ川をさか上ってきたが、途中に堰ができ上がってこれなくなり、今は琵琶湖で育った稚魚を4月中ごろに放流するとのこと。
量は年によって変わるが、
今年は17トン放流したという。8〜10センチの稚魚が、23センチぐらいまでに成長するという。
昭和30年ごろには、川に舟を浮かべ、鵜飼いも行われていたが、水量が少なくなり、とだえてしまったという。
漁協では、半天然鮎も扱っている。
和歌山の業者が琵琶湖の稚魚を池で育てたものだ。独自のエサを与えているので、普通の養殖鮎とは形も味も全く違うという。
この日も注文を受けてクール宅急便で全国へ発送されていた。
このあたりでは鮎は塩焼き、味噌だき、鮎ぞうすいなどでよく食べられていたそうだが、今では高価になってしまったこともあり、あまり食卓にのぼらないらしい。
ちょっと変わった食べ方を藤田さんに教えていただいた。
鮎を熱湯で4〜5分茹でてさまし、身をほぐす。これを味噌といっしょに煮るのだそうだ。鯛味噌はよく知られているが、これは鮎味噌といったところか。
保存食事でおかゆにそえて食べたそうだが、もう作る人も少ないという。
鮎は塩焼きが一番といわれ、内臓をとらず、ちょっと焦げ目がつくように焼き上げ、ほんのり苦いウルカを味わうためにも、頭からかぶりつくもよし、わが家では、この時期鮎めしを楽しんでいる。
|